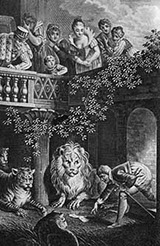二重否定の巻
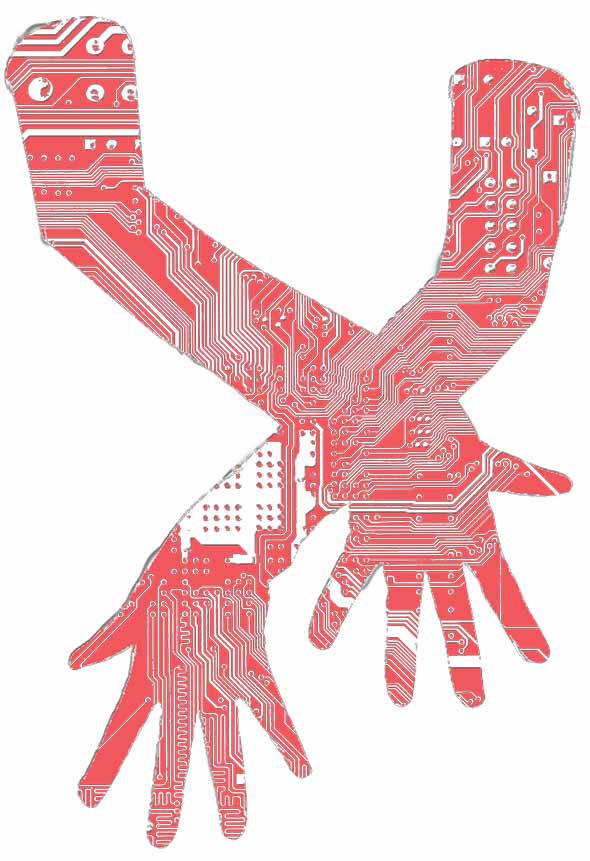
12歳くらいの時か。中学校で習い始めた数学でつまづいた。(プラス)×(プラス)=(プラス)だ。そりゃそうだろう。
でもなぜ(マイナス)×(マイナス)=(プラス)なんだ? コレがわからんために、その後の数学の理解はストップ。大嫌いになった。
長じても心の奥深くこの課題が残った。賢い奴はそう覚えておけばいい。と
スルッと通過する。大学の時に理数の奴に聞いたら「タケサン。敵の敵は味方やんかとさらり。おおそうか。納得度が上がったが、
どう式に結びつく?
でも敵は「ー」敵の敵は敵にとって「ー」。だから敵の敵は自分の味方「+」か。
そう言われれば、フーン。
ところで、その対立する項目を「掛ける」ってどういうこと?
「乗」と「積」。これって同質の積み上げじゃんか。価値の反転は?
数学でのプラス・マイナスが良し悪しとか、「正」「反」ポジ・ネガ・上下や
前後・左右の概念にまで対応するなんて子供にわかるかよ。
長い経験の上に重なり合って理解して行くんだなと。大人になってつくずく思った。
子供に(ー5人)×(ーみかん3個)=(+みかん15個)と言えば、なにっ?。
キョトンとするだろう。
5人にみかん3個つづ配ろうと思ったけどやめた。だから手元に今15個あるって
解釈してみるか(しっくりこないな)。
これ想いを含んでいるナ。物語を思ってしまう。それも切ないのを。
シラー にHandschuh(手袋)というバラードがある。18世紀の終わり頃の作品、
大意は以下の通り・
ローマ時代。あのコロシアムに王侯貴族・貴婦人たちがぎっしり集まる。
グラウンドに猛獣たちが次々と放たれ、あくびしたり、伸びしたり、
ゴロゴロしている時。
突如、バルコニーから手袋が猛獣たちの真っ只中に投げ込まれる。
さる貴婦人、傍らの騎士に「ねえあなた。いつも私のこと好き好き言ってるけど、
ほんとならあれ取ってきて」。
騎士はしっかりとした足取りで猛獣たちのたむろするところへ降りてゆく。
平然と群の中に入り、手袋を拾い上げ、ゆうゆうとバルコニーに戻る。
万場の観衆たちからは破れるような称賛の拍手。
と、騎士は手袋をその貴婦人の顔に投げつけ「拙者。何も願いませぬ」と
言って静々と去ってゆく 。
。
シラーは当時のサロンの淑女たちから総スカンを食らって書き直したとの話がある。
どのように直したのか不明
20年も昔、ツアーに混じってローマへ行った。コロシアムを見ての帰り、
ツアー客仲間たちと夕食。その席上でこのバラードの話をしたら、受けた。受けた。
これぞ典型的「二重否定構造」だ。貴婦人は「こいつの怯える姿が見られる。
それから猛獣に食われたらいい。 面白そう」と。
それが一転否定される。顔に投げつけられる手袋。なにも乞わない。と。
笑い者は一挙に貴婦人側に。そして静々と(カッコいい〜!)去る。
生きて帰れない。初めからわかってる。それを踏み越えて貴婦人に対抗する。
これって何? このドンデン返しの美学。
そうか、二重否定はソロバン抜きが報酬なのか。なら無償の報酬って何か。
その上、時空・構造・なにもかもを包括してたままで・・・・・と思う。
神の知恵?・法則?。
ユダの裏切り(ー)その結果、十字架上での死(ー)そしてイエスの復活と
救いの完成(+)。福音書の記述は明瞭な二重否定構造だ。
人間は経験的に二重否定の大きさ・奥深さを体得して行くのだろうか。
いや違う。美しいものを美しいと感じ取る能力と同じ。
生まれた時から持ってるんだろう。きっと、神から来ている公式だと思う。
この視点から福音書を吟味してはどうだろう。
いろんな所にナイフを入れてみるよう。その切り口から二重否定が見つかりそう。お〜、これよこれよ。パァ〜っと強烈な明かりを見つけ出したい。
あのバラード。投げつけられた手袋がイエスの十字架上の死と重なる。罪の死だ。
去って行く騎士の姿は復活後のキリストだ。
シラーはそれに重ねたのだ。きっと。